少子高齢化が進む中、多様な人材を受け入れる企業が増えてきました。
「外国人の優秀な人材を採用したい」とお考えの企業様も多いのではないでしょうか。
しかし、日本で外国人が就労するには、「在留資格(ビザ)」という法的な要件を満たす必要があります。
その中でも、多くの企業で採用されているのが「技術・人文知識・国際業務」という在留資格です。
この記事では、外国人採用を検討している人事担当者の方に向けて、この在留資格の概要や申請のポイントをわかりやすく解説いたします。

「技術・人文知識・国際業務」とは?
この在留資格は、専門的な知識や技術を活かして行う業務に従事する外国人が、日本で就労するために必要な在留資格です。
たとえば、以下のような職種が対象となります。
- システムエンジニア、プログラマー(技術)
- 経理、企画、マーケティング(人文知識)
- 通訳・翻訳、語学教師、貿易業務(国際業務)
一方で、単純労働(工場作業、清掃、飲食店のホールスタッフなど)は対象外となります。
この点は、外国人を受け入れる際に注意が必要です。
在留資格を取得するための要件
採用予定の外国人が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するためには、主に以下の要件を満たす必要があります。
(1)学歴・職歴
- 原則として大学卒業または専門学校卒業(職種に関連する分野)
- 学歴がない場合は、実務経験が原則10年以上必要(職種によっては3年)
(2)業務内容と学歴・経験の関連性
- 学んできた分野と実際に従事する業務との関連性が求められます。
例:経営学部卒の方がマーケティング業務に従事 = OK
(3)雇用契約の内容
- 正社員または契約社員としての雇用契約が必要です。
- また、出入国管理及び難民認定法施行規則に基づき、報酬(給与)は日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが求められます。
- 実際の業務内容や報酬水準が不適当と判断されると、在留資格の許可が下りないことがあります。

申請手続きの流れ
実際に外国人を採用し、在留資格を取得するためには、以下のようなステップを踏みます。
- 雇用契約の締結
- 必要書類の準備(企業側・本人側)
- 出入国在留管理庁への申請(在留資格認定証明書交付申請) → 日本に既に他の在留資格で滞在している場合は、在留資格変更許可申請
- 就労開始
審査には1〜2か月程度かかることが多いため、採用スケジュールに余裕をもって準備することが大切です。
必要書類(主なもの)
申請に必要な書類は、受入れ機関(企業側)の規模により区分されるカテゴリー(①~④)に応じて異なります。
■ 共通して必要な書類(外国人本人が提出)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚
- パスポートの写し
- 履歴書
- 卒業証明書および成績証明書(学歴がある場合)
- 職務経歴書(職歴がある場合)
■ 企業側が用意する書類(カテゴリーにより異なる)
企業の区分(①~④)により、必要な書類の内容が異なります。主に以下のような書類が求められます:
- 雇用契約書または内定通知書
- 業務内容説明書
- 会社案内、登記事項証明書
- 決算書や損益計算書などの財務資料
さらに、区分によっては次のような追加書類の提出が必要になります:
- 法人税の納税証明書(その1・その2)
- 源泉徴収義務者の届出書の写し
- 雇用保険適用事業所設置届の控え など
※詳細は出入国在留管理庁が公表する申請書類一覧表をご確認ください。
よくある不許可のケースと注意点
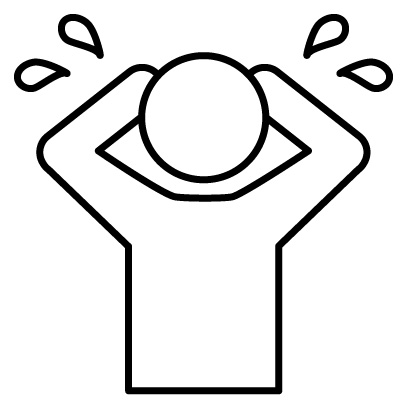
以下のようなケースでは、不許可となることがあります。
- 業務内容と学歴が関連していない
- 実際の業務が単純作業であると判断された
- 会社の経営状況が不安定
- 提出書類に不備や矛盾がある
- 実際の業務量が少なく、申請内容と乖離していると判断された
在留資格の審査は厳格に行われるため、採用したい人材が許可を得られないというケースも少なくありません。
だからこそ、事前の準備と正確な申請が非常に重要です。
まとめ:外国人採用を成功させるために
「技術・人文知識・国際業務」は、グローバル人材を活用したい企業にとって非常に有効な在留資格です。
一方で、申請には専門的な知識や的確な書類作成が求められ、社内で完結させるのが難しい場合もあります。
当事務所では、外国人雇用に関する在留資格申請を多数サポートしており、書類作成から申請代行、アドバイスまで一括して対応いたします。
「どこから始めればいいかわからない」
「うちの会社でも採用できるだろうか?」
そんな疑問や不安をお持ちでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。
企業様と外国人の未来をつなぐお手伝いを、全力でサポートいたします。

